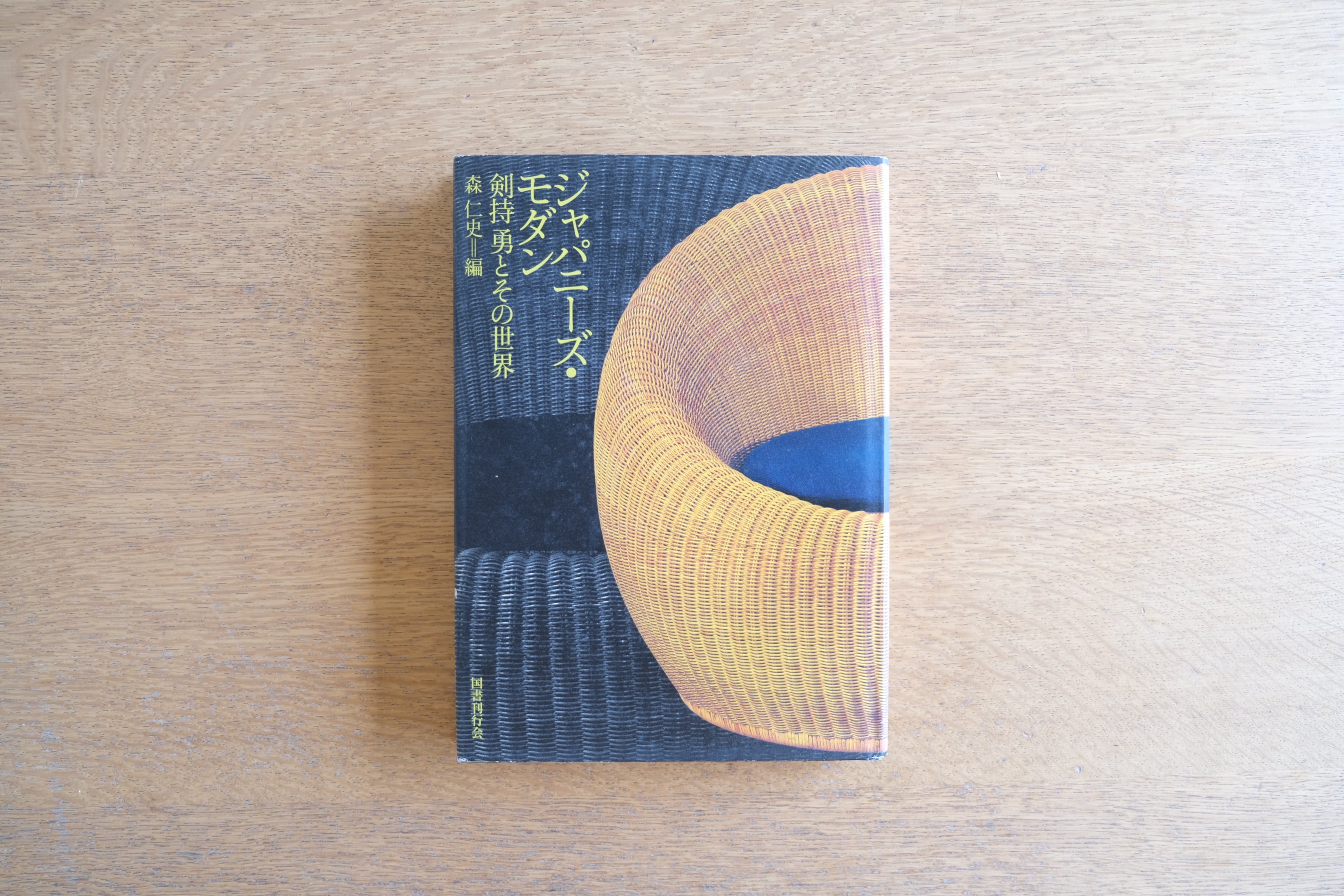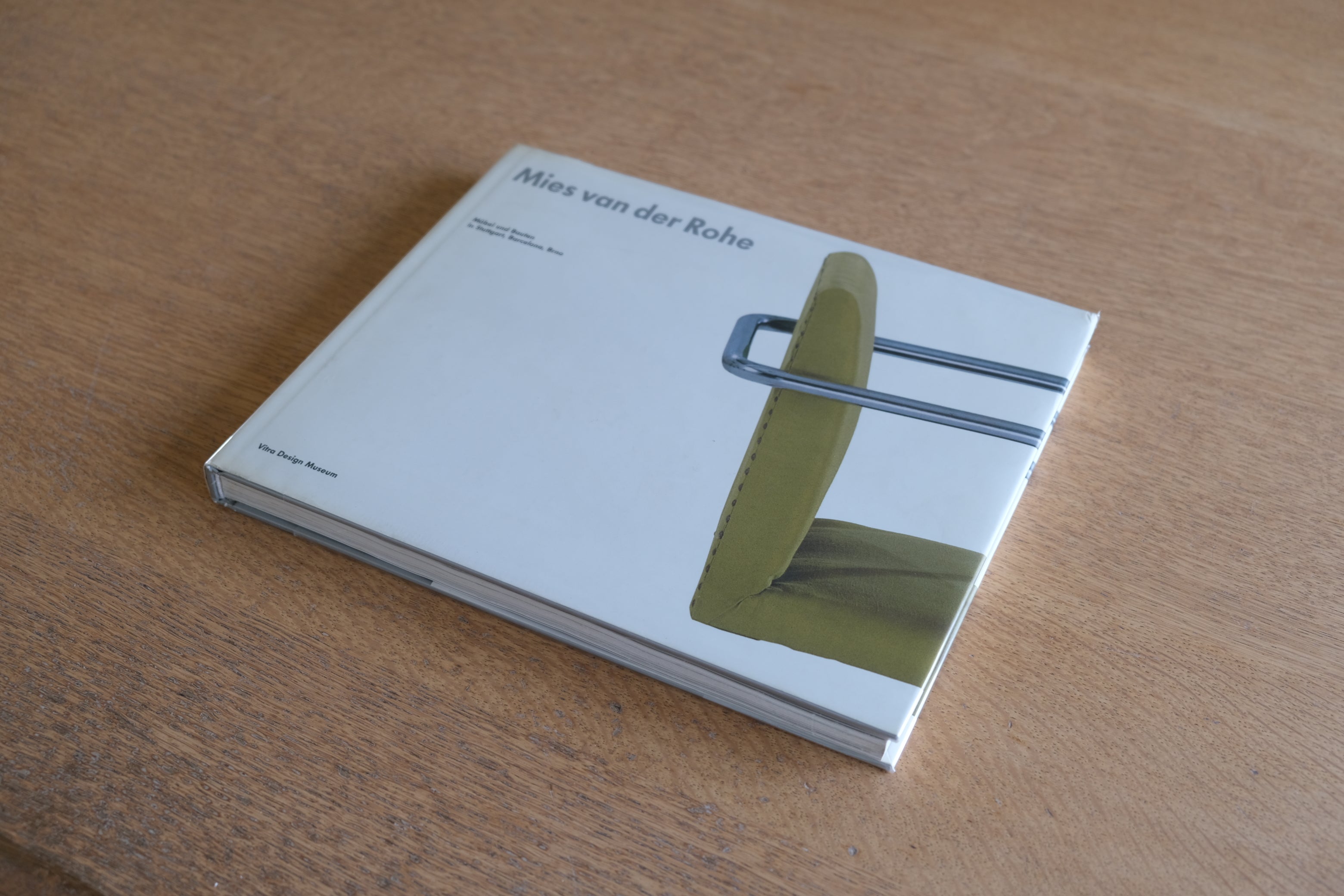意味の手触り|選ぶことは、想像力を手渡すこと。
ブログには、ふたつの種類があります。
目的や気分にあわせて、お好きなほうをお選びください。
お金がなかった頃、図書館の本に救われた。
割り勘が当たり前の時代に、惨めだと思った夜もある。
でもページをめくれば、世界は広がっていった。
想像力が、自分をどこへでも連れていってくれた。
本は情報じゃなかった。
生きる手触りだった。
国会図書館のデータベースを開けば、
昔なら“稀覯本”と呼ばれた本さえ、PDFで読めてしまう時代になった。
知っているか知らないか、それだけの差があまりにも大きい。
もはや「持つ」こと、「買う」ことには価値がないと言われても、
それは確かに一理ある。
でも、それだけで済ませたくなかった。
触れることでしか得られないものが、たしかにある。
FAXに光を見出すように、
インクのにじみや紙の重さに、
“意味の輪郭”が宿っていると思った。
言葉が届かないところにも、手触りは届く。
それは誰かの記憶を呼び覚ますものかもしれないし、
まだ言葉にならない未来を想像させるものかもしれない。
ぼくにはオンラインという武器がある。
でもそれは、人を切るためのものじゃない。
お師匠から受け取ったこの道具は、
想像力で世界を切り拓くために持たされたものだった。
検索ワードの奥に、まだ誰も語っていない文脈がある。
画面の向こうにいる誰かへ、
“意味を編集して届ける”という行為こそ、
いま、ぼくが選んだ仕事のかたちだ。
選ぶことは、過去を遡ることじゃない。
誰かの未来に、静かに種を蒔くことだ。
ぼくは「古書店」をやっている。
だけどそれは、“本を売る”というより、
想像力を渡す営みだと思ってる。
便利さの時代に、意味の手触りを届ける。
それができるなら、たとえ小さな店でも、
ぼくにとっては、十分な革命だ。
誰かの記憶を呼び起こす一冊を、
いつか誰かの未来に置いておけたら。
それだけで、この商いは意味がある。
読みものを楽しむ:
次回予告
来週木曜日(5月23日)は、
**「在庫のささやきを聴く——再出品の判断を“人間らしく”するための仕組み」**をお届けします。
売るか、残すか。
静けさをまとう在庫と向き合うことで、
“選ばないこと”の意味にも、少しずつ光が射してきます。