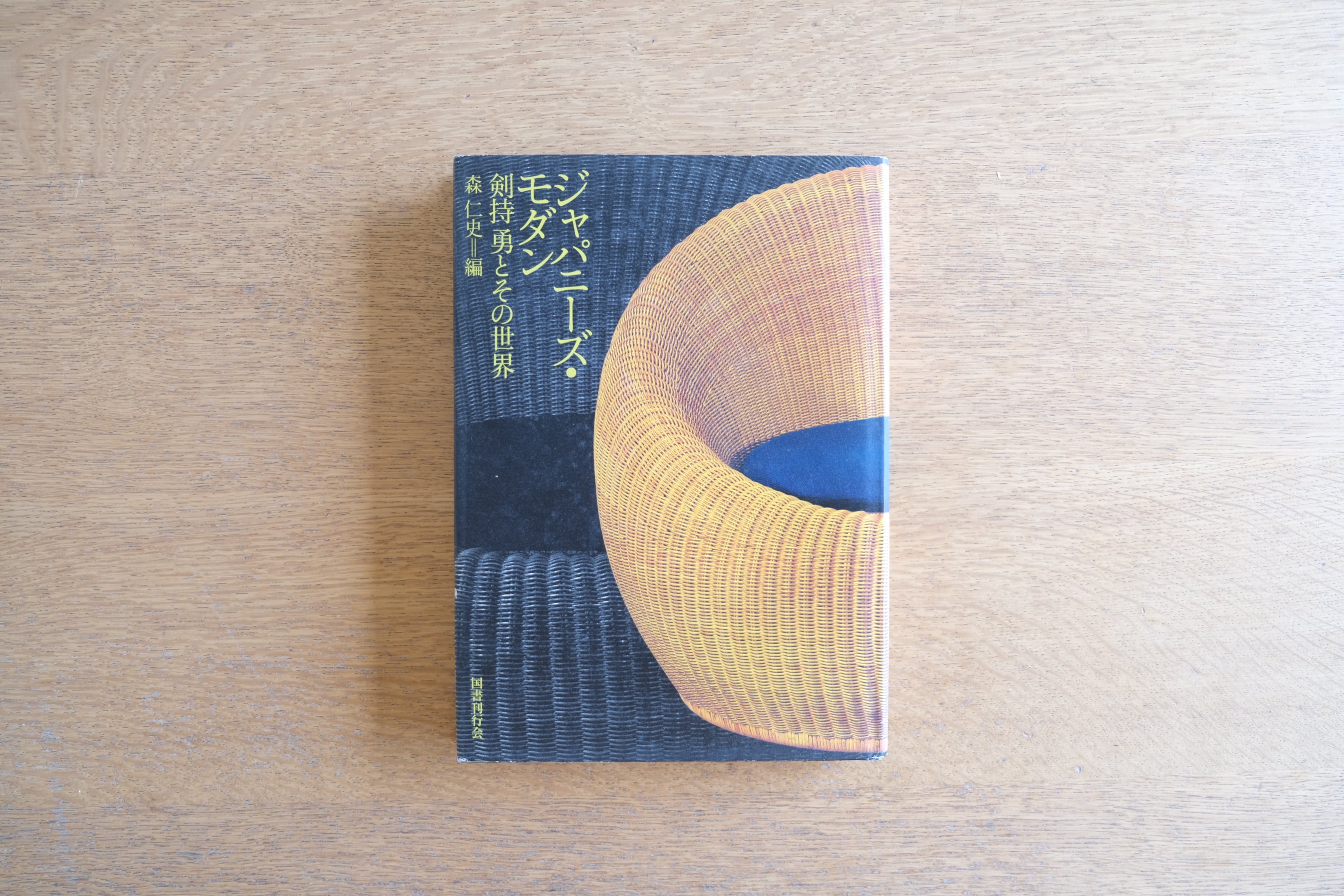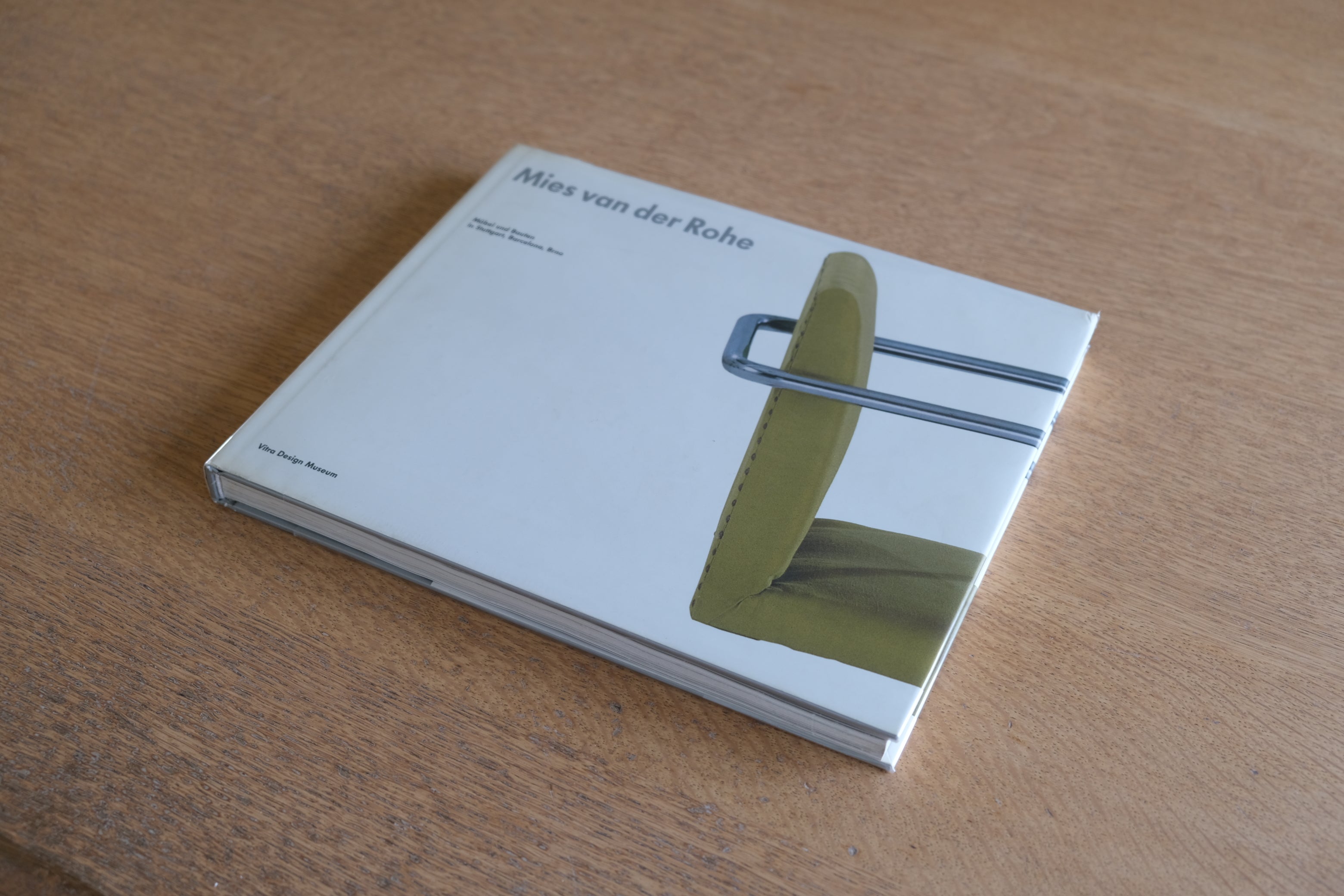売り抜けるという選択|不動産・株・家具に共通する出口戦略と暮らしの美学
出口戦略と暮らしの美学
買うのは容易く、売るのは難しい。不動産、株、家具、古書──形は違えど、同じ課題が横たわっている。
これは投資指南の記事ではありません。
モノを所有してきた人が、次の段階へ進むための「出口の設計」と「整理」の話です。
まんだらけの「生前見積」が示したもの
まんだらけが数年前から「生前見積」というサービスをはじめた。
いずれ訪れる終わりの時に備え、所有するコレクションをあらかじめ査定し、出口を設けておく。
これは単に古書の世界にとどまらず、あらゆる資産に共通する課題である。
不動産、株、家具。
いずれも「買う」瞬間は高揚感に包まれるが、難しいのは「売り」にある。
この出口戦略をどう描くかで、人生の暮らし方そのものが変わってくる。
私は日々、古書や家具の「入口」と「出口」の両方に立つ仕事をしている。
だからこそ、買う側の歓びと、手放す側の現実が、同じ場所に並んで見える。
天国へは何も持っていけない
資産を増やすことは、ゲームのように刺激的だ。
高級マンションを買えば理想の住まいに暮らせる。株や暗号資産で儲ければ、資産運用の効率に酔うこともできる。
だが、そのルールは残酷だ。
どれだけ蓄えても、最後には何ひとつ持っていくことはできない。
これは宗教やスピリチュアルの言葉を借りずとも、明快な事実である。
都心不動産と仕手株的な現実
都内のマンション価格は平均で「億を超えた」と言われて久しい。
しかし現場の声を拾えば、すべてが右肩上がりではない。
実際には仕手株のように価格が吊り上げられ、現実には値崩れしている物件も少なくない。
情報に触れるほど、親の仇のように物件情報やメルカリを探す人の姿が浮かぶ。
出物に出会う瞬間はたしかにある。
だが、その裏には必ず「手放す誰か」がいる。
老いてなお資産に執着する人もいれば、買値より安くても「手放したい」と考える人もいる。
正しいか間違いかは、外部が判断できるものではない。
ただ、その出口の設計にこそ人生観が宿る。
「買う」と「売る」は別物
株も不動産も家具も、「買う」という入り口は似ている。
市場に現れた瞬間を見極め、価格を比較し、将来の値上がりを想像する。
だが、「売る」となると話はまったく別だ。
売りの判断には、次の要素が絡む。
- 年代:若ければ時間を味方につけられるが、歳を重ねれば出口は近づく。
- 保有コスト:不動産には固定資産税、家具やコレクションには保管費や管理の手間がかかる。
- 市場の動き:価値が伸びるものもあれば、需要が急速に失われるものもある。
この「売り」のタイミングをどう設計するかが、資産の価値を最大化する唯一の方法といえる。
同世代への提案:出口を意識して一覧化する
もし私と同じ世代である40代前後ならば――
おすすめは「持ち物・購入金額・購入日・現在の相場」を一覧化し、出口を見立てることだ。
- どこで手に入れたか
- いくらで買ったか
- いま市場でどの程度の価値があるか
これらを冷静に記録しておけば、「最大化の局面で売り抜ける」という選択肢を合理的に取れる。
資産運用と同じく、エントリーだけでなくエグジットの設計が肝要である。
しかし、所有の本質は別にある
とはいえ、個人的な好みを言えば、数字上の最大化よりも「好きなものを見つけて買い、大切に愛用する」ほうが豊かだと思う。
含み益で楽しむことはあっても、本質は「使う」「愛でる」。
家具も一気に揃えるのではなく、少しずつ、自分の暮らしに沿うものを選び集めていくことに意味がある。
高級家具店に行けば、プロが一式をコーディネートしてくれる。
ホテルライクな住まいをすぐに整えることもできる。
だが、私にとってそれは完成品すぎて、感性に響かない。
未完成で、時間とともに整っていく暮らしこそが、自分らしい。
資産としての家具は機能するか
家具や古書は資産になるのか。
答えは「部分的にはYes」だ。
実際に名作家具やヴィンテージは国際市場で高値がつく。
しかし重要なのは、どこで手に入れたか。
新品で高額購入した瞬間に価値が目減りすることも多い。
一方で、セカンダリー市場や海外で見つけた品なら、時に大きなリターンを生む。
ただし、寝かせて10年先に価値が跳ね上がるものを買い揃えたとしても、その間にキャッシュが尽きれば意味がない。
「売り抜ける」戦略を描かないまま集めすぎれば、資産どころか負債になる。
出口戦略と暮らしの美学
結局のところ、資産の出口戦略は冷酷な数字の論理にすぎない。
しかし暮らしの美学はそこに留まらない。
人生を動的にとらえ、旅や経験に投資する人もいる。
逆に、日常の中でモノを愛で、静かに豊かさを育む人もいる。
どちらも正解で、議論すら不要だ。
大切なのは、自分の人生観に即した「出口の形」を描くこと。
売り抜けて資産を最大化するのもよし。
最後まで愛用し、手放さずに生を全うするのもまた美しい。
結びに
買うのは容易く、売るのは難しい。
不動産、株、家具――形こそ違えど、その本質は共通している。
出口戦略を意識すれば、資産としての側面を強化できる。
一方で、愛着をもって暮らしに根づかせれば、資産を超えた豊かさを得られる。
そのあいだで揺れるのが、人の生き方であり、モノとの関係の奥深さである。
だから私は、売るために集めるのではなく、
いつか手放すことを前提に、選んでいる。
関連記事
👉 関連記事:
天国へは持っていけないけれど:ものを所有することの意味と価値
この記事について
本記事は、選品舎/Helvetica を運営する大西健が執筆しています。
ヴィンテージ家具・古書の選品、販売、記録を通じて、
「残るもの/残らないもの」の判断基準を実務の中で整理しています。
この判断軸の全体像は、残るものを選ぶという行為についてに記録しています。